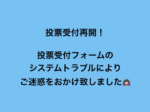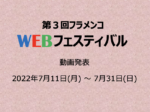- Home
- WEBフェスティバル, フラメンコ2030情報
- 第5回フラメンコWEBフェスティバル 全20作品紹介&コメント
第5回フラメンコWEBフェスティバル 全20作品紹介&コメント
- 2025/9/1
- WEBフェスティバル, フラメンコ2030情報
5回目を迎えたフラメンコWEBフェスティバル。世界的なパンデミックでライブどころか外出すらままならなかった2020年。スペインも、日本も、フラメンコを取り巻く状況は大きく変わってきました。世界的な観光ブーム?からスペインではタブラオが増え、フェスティバルも盛況です。日本では先日、ガルロチ年内閉店のお知らせもありましたが、航空運賃やホテル代などの経費の高騰、まだ劇場不足などからスペインからのアーティスト招聘も年々難しくなってきているようです。物価の高騰などで生活に余裕がなくなって、“趣味”としてのフラメンコをにかかるお金を節約せざるを得ない状況の人もあることでしょう。そんな中でも、フラメンコが自分の一部、人生、生活の一部になっている人たちは、そんな中でもなんとか、自分でフラメンコに親しむ、フラメンコを楽しむ方法を探すのではないでしょうか。お教室やライブに通うだけがフラメンコではありません。動画を見たり、録音を聞いたり、それを真似してみたり、またまた関連する本を読んだり、と楽しみ方は無限大。このWEBフェスティバルに参加するため、アイデアを色々考えて試行錯誤することや、ビデオのために練習に励むことも、過去の映像を見返して編集することも、フラメンコの楽しみの一つなのではないでしょうか。今回も全20作品の感想コメントを書かせていただきました。
エントリーNo.1 JOB/アコギソロ オリジナル曲「気まぐれな風」

元々クラシックをかなり弾いていらした方なのでしょうか。クラシックギターで奏でられるフォリア(15世紀末イベリア半島で生まれ、17、18世紀の欧州で大変ポピュラーだった舞曲でソレアやブレリアの祖のひとつとも言える三拍子の曲)のような感じで始まります。フラメンコダンサーとのコラボで作曲したオリジナルということですが、これならブレリアやファンダンゴ風味で踊る方も無理なくできたのではないでしょうか。
エントリーNo.2 TERAMAKIxyuko/夢フラメンコ十夜――こんな夢を見た/Siguiriya

お寺の本堂でしょうか、大きな仏壇の前でのパフォーマンスを編集したもののようです。音楽もきっとその時のものなのでしょうね、ライブ録音のようです。曲は通しで流しているものの、踊りの方は編集されているので、イメージビデオみたいな感じですね。これは作品として夢十夜全編を公演したものなのでしょうか。それとも、その予告編という感じなのでしょうか。もしくはフラメンコで自分の持つイメージを具体化しようという意気込みを感じます。
エントリーNo.3 森山みえ、富松真佑子、吉平梓、柴田万裕子/Maria Magdalena/Plazuelelo(Fiesat) Luis Moneo

スタジオですね。バックとなっているカーテンの奥は窓なのか鏡なのか。カーテンの前に椅子やマントン、靴などが置かれています。ヘレスのルイス・モネオのブレリアの録音で踊るところが編集されている映像です。同じ振り付けを踊っていても、ちょっとした首の傾げ方や目線、腕の位置、表情などの違いでそれぞれの個性が見えるのがとても面白いし、フラメンコらしくて良いですね。黒い衣装、赤い衣装、フォーメーションの違いなどを上手に編集してますが、元の動画の録画にはたくさん時間がかかったことでしょう。
エントリーNo.4 『気軽にフラメンコ』の仲間達/ウナ・パタイータ/パルマで踊ろう♪

スタジオで仲間のパルマで一人ずつちょこっと踊っていきます。思い思いの衣装、思い思いのパタイータ。それぞれに楽しんでいる感じがいいですね。ブレリアでウナ・パタイータを踊るというのは初心者の憧れ。取りああえず挑戦してみようという意気込み、頼もしいです。パルマにちゃんとアクセントがつくともっとブレリアぽくなるのではないでしょうか。今度は録音のフィエスタ・ポル・ブレリアをランダムにかけて踊ってみるというのにもぜひ挑戦してみてください。
エントリーNo.5晃&舞雪子親子/父と娘でフラメンコ/さくらさくら

フラメンコが専門じゃないけどギターが得意なお父様との親子共演、いいですね。バックに額が飾られた、和の雰囲気の会場でのライブ録画のようです。フラメンコ以外の曲をフラメンコのテクニックで踊るというのではマリア・パヘスが有名ですが、ここでは日本の曲ということにちなんでか、アバニコも日本舞踊のように手で持って開いたりしている、その工夫もいいと思います。また、馴染みのある曲を使うことで、フラメンコが初めての人にも親しみやすくなるというのもあると思います。
No.6 島袋紀子・Andy/Mi vida Sevillana 〜今日は火曜日〜/ホルキージャ、タンゴ

セビージャ在住の島袋さん、その日常生活の様子を同じくセビージャ在住ギタリストのアンディさんのギターをバックにみせ、お勤め先のフラメンシューズ専門店で踊っている様子を入れ込んでいます。そうなんです、セビージャにいるというだけで全てがフラメンコになるということはなく、ご飯用意したりバスに乗ったり仕事したり、日々のルーティーンが続きます。それでもフラメンコの歌詞に出てくるものがいっぱい身近にあり、フラメンコのベースになっている文化の中にいるのも確かです。バス停での足の復習や鏡見てブラソちょっとやってみる、なんていうのは身につまされる練習生も多いのでは?
No.7 タマラ/Venga Pepe/Venga Pepe(ブレリア)

このフェスティバルの醍醐味は日本全国位や世界中のフラメンコ好きな日本語話者がそれぞれにフラメンコを楽しんでいる様子を垣間見ることができることだと思うのだけど、参加されている方の中にはフラメンコをなりわいとしているプロの方もいて、そんな方たちのパフォーマンスを観ると、やはり違うなあ、すごいなあ、と思わされるのであります。タイトルだけ知っているけど私はまだ観ていないアニメ映画のサントラからのドラマチックなブレリアを海辺で踊っています。サパテアードは畳半畳ほどの大きさのコンパネの上で。小さいスペースでも大きく踊ることができるといういい見本ですね。それにはやはり身体の使い方、腕や上体の使い方がポイントとなってくるように思います。
No.8 今城直子/El Gran Derbi de Sevilla/セビジャーナス

これはすごい。フラメンコ揺籃の地セビージャのサッカーを題材にしたセビジャーナス。セビージャのサッカーチームのユニフォームとマフラーをしてるだけかと思いきや、なんとスペイン語でデルビを歌ったセビジャーナスの替え歌まで歌いながら踊っている! この方はベティスファンということでデルビを歌うと言いつつ、結局ベティス万歳になっているのも微笑ましい(ということにしておきましょうと思う私はセビージャ・ファン)。ちなみにイスラエル・ガルバン、ジェルバブエナ、ハビエル・バロン、ラファエル・カンパージョ、ホセ・デ・ラ・トマサらはベティス狂。ボボーテやフアン・カンパージョ、マノロ・ソレール、古いとこではカラコールがセビージャ派。ベティスのラジオにはフラメンコ番組があってゲストで出演したフラメンコ・アーティストも多いとか。細かいことを言うとスペイン語なはずなのに読み方が英語混じりだったり、訳のティがディになってたりとか、ありますが、これ、まじ、ベティス本部に送ってあげたい。
No.9 日本に恋した、フラメンコ(永田健)/フラメンコで学ぶ古事記/「ヤマトタケル」ダイジェスト

プロによる公演から抜粋編集したもの。古事記という日本の古典を題材に、日本語の歌詞をフラメンコの伝統的なメロディ、リズムにのせて、フラメンコの技術で踊るという意欲作。和装というか、古代風?の衣装にスペインのアバニコを合わせたり、謡風というのでしょうか、お腹から声を出す発声とフラメンコ音楽やスペイン語の不思議な組み合わせなど、さまざまな工夫の上、フラメンコで日本の古典の物語を伝えようという試みは非常に興味深く、全編を見てみたくなりますね。ということはプロモーション動画としても成立している? 歌舞伎でファイナルファンタジーやナウシカ、ワンピースなどを作品にする時代ならではのフュージョンだとも思います。
No.10 KANA MENDOZA ROBERTO MENDOZA 、TAKEJANDRO CASTAÑA MARTÍNEZ /SEVILLANAS A LA MEXICANA

メキシコ人だというご主人が歌うセビジャーナスをメキシコの民俗衣装で踊っています。最初、動きが小さいなと思ったら実は頭の上に蝋燭を乗せていたという。これはメキシコ、ベラクルス地方のラ・ブルハ、魔女という踊りからなのでしょう。かと思うとマントンやアバニコを使ったり、と工夫して変化をつけています。中南米とフラメンコの深い関係は、カンテ・デ・イダ・イ・ブエルタ(行きて帰りし歌)などでもお馴染みだと思いますが、メキシコについていえば、フラメンコ曲ペテネーラの起源がメキシコの同名の歌にあったことが近年明らかにされました。またメキシコ出身、スペイン在住のフラメンコ舞踊家がこのメキシコのペテネーラを踊ったりもしています。またメキシコ出身のフラメンコ舞踊家もカスタネットで有名なルセロ・テナやルイシージョ、ピラール・ロペス舞踊団で活躍したロベルト・ヒメネスやマノロ・バルガスなど来日公演をしている人も多いのです。メキシコはスペイン、日本に次いでフラメンコ舞踊教室が多いという記事も検索で見つかりました。大規模なフェスティバルもやっていますね。ご参考までに。
No.11 東郷恵子(Bacante)/好きな歌がある幸せ、喜び、Alegrias/Bahía de Cádiz (Alegrias)

カンテソロ。まっすぐ前に大きな声が出ているのもそうですが、歌うことを心から体全体で楽しんでいるのがいいですね。曲はカマロンが1979年のアルバム『レジェンダ・デル・ティエンポ』で歌ったものですね。シレンシオがはいる、舞踊のアレグリアスのスタイルで録音しているのがめずらしいアレグリアスです。そのスタイルをサリーダ(カマロンはサリーダ無しでギターのイントロからすぐレトラに入ります)以外、そのままの順番で歌っています。フラメンコではいろんなレトラを古典から新作、自作まで、あちこちからとってきてとり混ぜて歌うことが多いので、そのまま歌っているのはカンシオン的な感じにも聞こえるんですが、確かにこのほうが歌う人としてはアプローチしやすいというのがあるのかもですね。朗々とエネルギッシュに、前乗りで歌い上げるだけでなく、ニュアンスをつけてしっとりとというようなタイプの曲も歌っていらっしゃるのかな。気になります。
No.12 Lola y Juan/Fandangos por Solea/De amore’ y desengaño

こちらもカンテソロ。アメリカ在住のアフィシオナードさんです。2016年に亡くなったウトレーラの歌い手ペパ・デ・ベニートのアルバム『ジョ・ベンゴ・デ・ウトレーラ』収録のファンダンゴ・ポル・ソレアを丁寧に、気持ちよさそうに歌っていきます。この歌が好きで一生懸命勉強したんだろうなあ、と感じさせる歌いっぷり。フラメンコは、これが好き、という気持ち、愛こそがすべてだと思うのです。そしてフラメンコには(にも、かな)終わりがありません。あの歌に近づくためにはどうすればいいか、聴いて聴いて聴き込んで、他の歌も聴きまくり、ってしていくんですよね。いやあ、大変な世界です。アメリカも、フラメンコの歴史のごく初期からスペインのアーティストたちが公演をしたり、とフラメンコが関係が深い国の一つです。今もフェスティバルをはじめ、公演も定期的に行われていますね。スペインでも日本人のフラメンコ愛、アフィシオンは有名ですが、アメリカに限らず、フランスやドイツなどスペイン以外の国在住の日本人フラメンコファンって多いんです。日本でフラメンコをはじめていた人もいるのですが、やはり日本とフラメンコは特別な関係なのかもしれません。謎です…。
No.13 verchilo(ベルチロ=森野みどり、凌木智里、LOLA)/¡Somos verchilo, olé!/Bulería,Sevillanas,Rumba

フラメンコで楽しもう、フラメンコを楽しみつくそう、といういい意味での貪欲さを感じられるトリオ。踊って歌っておちゃらけてとにかく楽しい動画です。でもおちゃらけだけじゃないよ、というのはゆっくり踊るセビジャーナスのブラセオ、腕の美しい動きからも分かりますね。というか、基本ができてないとおちゃらけることは不可能です。フラメンコというとジプシーの苦しみから生まれましたとか安易に言いがちですが、そんな単純な話ではありません。苦しみや痛みも身近なテーマとして取り上げられることが多かったのも確かですが、苦しい生活だからこそはじけよう、笑おうというのもフラメンコ。シリアスな叫びも、ユーモアのある楽しいものも、どちらもフラメンコ。そのどっちが上とか下とかもありません。ここではライブ映像に過去のWEBフェス参加の映像を混ぜて上手に構成しています。いやあ、今後どんなふうに展開していくかというのも楽しみなグループです。
No.14 中村一郎/代田橋ペガサスにて/ガロティン

第1回から欠かさず参加してくださっている中村さん、いつも個性的な味わいのあるカンテを聴かせてくださいます。常連の方の動画は、今回はどんな曲をどんな風に見せてくれるのだろう、と観る前から楽しみなのですが、今回のガロティン、これまで以上に素晴らしかったのではないでしょうか。任にあっているというのでしょうか。声もよく出ているしリズムにもうまく乗っかっています。きっと明るい性格の方なのでしょうね。最後の笑顔もいいですね。また最初にスペイン語で紹介するなど、スペイン語も勉強していらっしゃるのですね。素晴らしいです。
No15 アリアーテ東新宿、稲津清一、那須慶一/アリアーテ東新宿 スタジオライブ 「ライブ 壱(イチ)」/カバーレス

フラメンコスタジオでのカンテリサイタルから一曲、選んだのがカバーレスというのが渋すぎます。カバーレスはシギリージャの終わりに歌われることも多い、長調に転調したシギリージャといえば、あ、と思い当たる方もいるかもしれません。スペインの歌い手でもリサイタルでカバーレス歌うなんて人まずいません。それもポピュラーな「モリートス・ア・ピエ(ムーア人は馬に乗って)」という歌詞ではないのにも驚きました。どちらで勉強なさったのか気になります。日本のアフィシオン、すごいですね。声もまっすぐよく出ているし音程もいいし、お上手だと思います。リズム系も聴いてみたいですね。
No.16 Akari Yamada 山田あかり/Siguiriyas al Golpeシギリージャス•アル•ゴルぺ/Siguiriyas al Golpeシギリージャス•アル•ゴルぺ
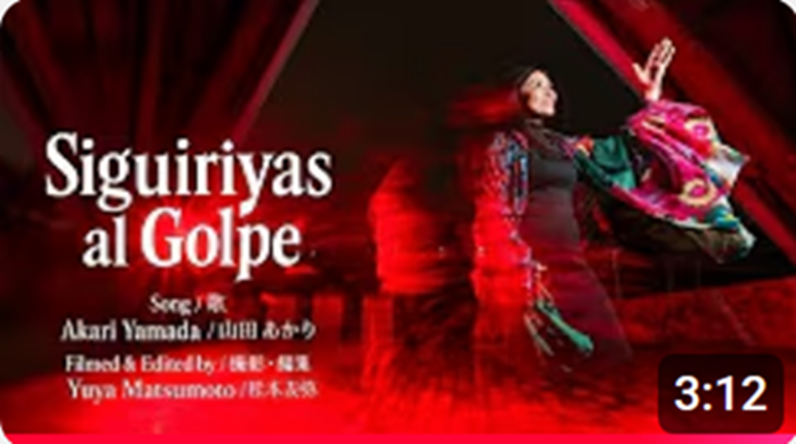
無伴奏でのシギリージャ。スピード感がある発声で、歌い慣れているというのが聴く側にも安心感として伝わってきます。歌詞の意味、方向性をかなり理解して歌っているという感じです。たくさん勉強して、いっぱい努力してここまでこられたのでしょう。でも、ここまで歌えるのだったらさらに上を目指していけるはず、と聴いている方としてはもっとああすれば、こうすればとつい色々考えてしまいたくなるような、そんな歌い手さんです。
No.17 ALEGRIA/~101匹わんちゃんより愛をこめて~/TANGOS

コメントからすると教室の有志によるライブの一場面のようですが、単に習った曲を踊るのではなく、101匹わんちゃんのダルメシアン犬のイメージで衣装を白黒の水玉にして耳をつけて、という発想がいいですね。そして先生がダルメシアン犬の毛皮を集めてコートを作ろうというクルエラ!役で登場。ここまでやるなら映画もしくは物語の一場面をイメージさせるような動き、クルエラが犬たちを追っかけ回すとか、があっても良かったかも、とか余計なお世話で思ってしまいました。でも本当にちょっとした工夫で発表会的な振り付けも面白くなるといういいお手本ですね。
No.18 栗原武啓/Buleria/Buleria

今回唯一のギターソロはブレリア。気負うことなく自然体で流れるように、見事に演奏しています。プロなら当たり前?いやいや、伴奏でたくさんの舞台をこなしているスペイン人のプロでもいざソロとなると、ファルセータの羅列で、起承転結なく終わったりする人もいますし、コンクールなどにソロで参加する人でも、澱みなく、コンパスをキープして、まとまった一曲を弾きこなす人ってそんなに多くなかったりするんですよ。伴奏には伴奏の、ソロにはソロの難しさがあるのです。フラメンコ協会の新人公演でもギター参加者が少ないと言われていますが、数曲踊ることができればプロを名乗ることも可能な舞踊と違い、一通りなんでも歌、舞踊の伴奏ができないとプロを名乗れないギターの方がやっぱりハードルが高いのでしょうね。
No.19 入交恒子/summer/Idan Balas : Eres Natural

兎にも角にも美しい作品。踊り手と衣装さんの共作とのことですが、ビデオ、音楽も含めこれぞプロのお仕事。という感じです。白のバタ・デ・コーラにマントンでの白鳥のような姿、片袖にマントンをあしらったもう一枚の衣装での姿、そして炎のような赤い衣装で、踊っている人が同じとは思えないくらい変身。片袖が着物のようなオリジナリティあふれる衣装で見せます。音楽は初めて聴いたのですが、セビージャにもいたことのあるイスラエルの人のようですね。彼にもぜひみてほしいですね、フラメンコに国境はないのです。
No.20 miyuki del mar/DUBでウォームアップ/We are one planet

レゲエをかけてフラメンコ。練習生の日常の練習風景のぞいているような感じがありますね。著作権フリーじゃなくても、YouTubeで使用可能な曲だったら良かったはずなので、次回はぜひ、いつもウォーミングアップで使っているお気に入りの曲で参加してくださいね。もしくはお気に入りの曲に振り付ける? レゲエに合わせて南国風?の大きなお歯のプリントのスカートにTシャツというのもいいですね。
今年も勝手な感想で失礼いたしました。今回はプロの方の、プロモーションビデオとして使えそうな、本気の動画が目立った印象ですが、セミプロやアマチュア、全国、いや全世界にいらっしゃるフラメンコを愛する方々のフラメンコ愛を垣間見ることができたのが、やはり個人的には一番うれしいことでした。改めてフラメンコの魅力の大きさを感じさせられたように思います。好きが一番大切。それは日本でもスペインでも、プロでもアマでも変わりません。これからもあなたの好きをエネルギーにフラメンコを楽しんでいきましょう。
受賞された方、おめでとうございます。受賞しなくてもフラメンコと出会い、フラメンコを楽しみ、それをみんなにアピールもできてしまうあなたは優勝、つまり全員優勝だと思います。みなさま、もっともっとフラメンコを愛してどんどん楽しんでくださいね。