和己も歩けば・・・〜フラメンコの森で〜
vol.26 再生
文/白石和己
Texto por Waki Shiraishi
Foto por Tomoko Ozawa

桜の話とは季節外れのようですが、私がこれを書いているのはまさに桜の時期なのです。そして同時にCOVID-19の影響で外出自粛まっただなか。不安や落胆に負けまいとせいいっぱい歩き続けるフラメンコの世界に、祈りをこめて解き放ちたい、1本の木のお話です。
![]()
その特異な桜に出会ったのは、1996年の4月のことでした。私は上七軒の萬春さんにいました。萬春さんは、もともとお茶屋さん。オーナーの伊藤かよ子さんがそこを改装してフレンチ洋食のレストランにしたのです。1階のカウンター席は、有名無名問わず、成熟した文化人たちが気取らず立ち寄る場にもなっていて、舞台や展覧会の話が飛び交い、これからはばたく若者たちを応援する空気が満ち満ちてもいました。ある舞妓さんと仲良くなったのをきっかけに訪れるようになった私も、ここで知り合った写真家の松尾弘子さんに『西陣グラフ』の連載エッセイのお仕事をいただき、それが婦人画報の連載や、本の出版につながって、物書きとして駆け出すことができたのです。
とはいえ駆け出し。そんな私に、かよ子さんや松尾さん、ときには常連のお客さまたちが、いつも何かご馳走してくださいました。京都なのに? そう、京都なのに。思えば不思議なところでした。信頼できる人からの紹介はたしかに大事でしたが、「文化を愛する、京都が大好きな、夢に向かってがんばっている若者」はとても大切にされ、よく言われる「勧められても3回断れ」的なルールは適用外でした。
「うちらに返すこと考えんでええから、いつか誰かを育てられる人になりよし」
そんな言葉と一緒に、目の前に素晴らしく美味しい「シチューの壺煮」が出されるのです。
今はかよ子さんも松尾さんも天寿を全うして天国に行き、萬春さんの跡地には違うお店が建っています。その分とても懐かしいです。ここでのエピソードを語り出すとキリがないので、またの機会に。
何はともあれ、私はあの日もそこにいました。いとたのしき春の夜でした。すると常連さんらしき人が入ってきて、こう言うのです。
「御所の松と桜な、心中しはったえ」
「え?」という顔になった私に、まわりが口々に説明します。
「桜松いうてな、松やけど、桜なんや」
「花は桜、せやけど、外側は松やねんな」
「そやそや。わかるか?」
わかりますかいな。ますます「??」になった私を面白そうに見て、かよ子さんが言いました。
「ほんなら、まっちゃん(松尾さん)と見に行ったらええわ」
「桜松」と呼ばれるその木は、京都御苑の西側、学習院跡と言われる場所にあります。見た瞬間、私は息を呑みました。1本の木が根こそぎ倒れていました。見上げるものだとばかり思っていた花々が、足元にほの明るく、散らばるように咲いているのは衝撃的な光景でした。そしてたしかに幹は松。枝と花は桜。ゆっくり聞いてやっと理解できました。空洞化していたクロマツの上部の虚にヤマザクラの種が落ち、根を下ろして育ったのだそうです。それが満開の花をつけたまま倒れたのでした。私はただ立ち尽くしていました。春の夜風の中で胸がしめつけられました。木はもう死んでしまうのだと思ったから。「何か書かなきゃ」という思いに突き動かされましたが、すぐに形にするには人生経験が足りなすぎました。
この日の記憶が、松と桜と風と嵐の織りなす一編の童話になったのは、それから約10年後。その間、私は知りました。人々が根本に土をかぶせて見守る中、桜松が見事に生き延びたことを。この作品は2016年、先に朗読音楽劇「さくらまつ」として世に出る機会をいただき、さらにこの初夏、銀の鈴社から出版が決まりました。ただ私はこのエッセイをその宣伝に使うつもりで書いているのではないので(読んでいただけたら嬉しいですが!)、次に行きますね。今日伝えたいのは、本物の桜松の、今現在のお話です。

桜松は今も健在で、今年も美しく咲きました。しかも驚くべきはその姿。20年以上の月日を経て、幹は倒れたまま苔むしており、その幹から出た枝々は、もう地面に這ってはいません。上に向かって突き上がるように伸び、そこに花が咲くのです。枝の上部は高く空へと向かい、もう飛び上がっても手は届きません。中にはすでに第二の幹のように太くなり始めている枝もあり、地面に接しているところからは根が生えているようにも見えます。尊厳の復活。強靭な生命力。
2018年の夏に襲来した巨大な台風による被害は京都御苑でも甚大で、100本以上の木が倒れてしまいましたが、桜松は、この形がゆえにどっしりと耐え抜くことができました。一方で、星のような形をしたひとつひとつの花の美しさはかつてと同じ。体にも松の名残りをとどめ、桜松としての個性も失ってはいません。
自分としてしか生きられない、けれど、自分として生きるためなら、わずかばかりの機会を活かし、表面的な形が変わろうとも生き抜くのです。シンプルに。
ほかの多くの業界と同様、フラメンコ界に、あるいはそこに生きる個々の人々に残されるCOVID-19の爪痕は痛々しく、その深さは現段階では想像もつかないものです。私には今、そこに何か、きれいで安易な激励を発信することはとてもできません。せめてこの号が出るときには、「フラメンコ界に残された爪痕」と過去形にできる状況になっていることを願うばかりです。
ただ同じ自然の一員として桜松から得られるものがあるとすれば、危機的状況に見舞われても、根っこが無事ならまた芽吹くということ。もっとたくましくさえなれるということ。もちろんそれは、フラメンコにとっての「根っこ」とは何か、「そこに土を被せる」という行為に値するものは何かを考えることなしには片手落ちです。そしてそこが現実的には一番大変なのだとも思いますが。
少なくともフラメンコの灯が消えてしまうことは絶対にないはず。なぜなら私が思うに、フラメンコの真の根っこは、ひとりひとりの心の中、目に見えないところにあるものだから。目に見えないものは、誰にも、何にも壊すことはできないのです。
問題は、目に見える形として復活させるために、どんな土をどう被せるのか。それは簡単ではないでしょう。桜松が人間の力と年月を必要とし、以前と同じ形に固執しないことで生き延びたように、ある種の忍耐力と柔軟性も試されるでしょう。精神的、金銭的な負担も伴うかもしれません。でも。
「生きる力、もらいますなあ」
「そうですなあ」
いま桜松を見る人は、そんな言葉を、心から、しみじみと口にします。これが未来の観客の言葉になることを信じて。フラメンコ界の真ん中にいるわけではないからと無力を感じるその手の中にも、何かの土がすでに握られているかもしれません。

 クラス情報
カテゴリ: クラス情報, フラメンコ各種情報
クラス情報
カテゴリ: クラス情報, フラメンコ各種情報
 第5回フラメンコWEBフェスティバル 開催します!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
第5回フラメンコWEBフェスティバル 開催します!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
 アーティスト情報
カテゴリ: アーティスト情報, フラメンコ各種情報
アーティスト情報
カテゴリ: アーティスト情報, フラメンコ各種情報
 第5回フラメンコWEBフェスティバル スポンサー賞ご紹介!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
第5回フラメンコWEBフェスティバル スポンサー賞ご紹介!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
 第3回フラメンコWeb フェスティバル 全ビデオ紹介/感想コメント
カテゴリ: フラメンコ2030情報
第3回フラメンコWeb フェスティバル 全ビデオ紹介/感想コメント
カテゴリ: フラメンコ2030情報
 萩原淳子ラ・ウニオンで優勝
カテゴリ: スペインでの日本人フラメンコ, ニュース
萩原淳子ラ・ウニオンで優勝
カテゴリ: スペインでの日本人フラメンコ, ニュース
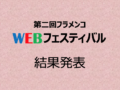 Flamenco2030 第二回フラメンコWeb フェスティバル 入賞者発表!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
Flamenco2030 第二回フラメンコWeb フェスティバル 入賞者発表!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
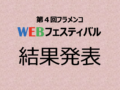 Flamenco2030 第4回フラメンコWeb フェスティバル 入賞者/スポンサー賞発表!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
Flamenco2030 第4回フラメンコWeb フェスティバル 入賞者/スポンサー賞発表!!
カテゴリ: フラメンコ2030情報
flamenco2030@gmail.com
Copyright © フラメンコ 2030 All rights reserved.